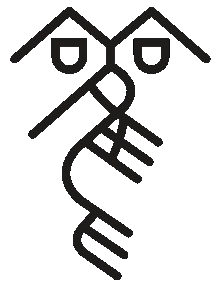神楽の演目を大特集!三大神楽の全演目と見どころをご紹介

神社やお祭りで行われる神楽ですが、その演目について知らない方も多いと思います。
神楽は神様に奉納される舞なので、その演目は神話に基づいた神様のお話が多いのです。
ここでは神楽の演目について、有名な神楽の演目を中心にご紹介していきます。
この内容を知っていることで、より舞の意味を理解でき、さらに神楽の世界を楽しめると思います。
神楽の創作舞はこちら
神楽の演目について
演目は場所により様々
神楽の演目は各地方により様々です。基本的には神様に捧げる舞になりますので、神様を崇める内容の舞になっています。
特に古事記・日本書紀に登場する神々の物語がベースとなっているものが多くみられ、おそらく皆さんも一度は聞いたことのあるお話ではないでしょうか。その地方特有の伝説などの場合もありますので、事前に物語の内容を調べておくとより鑑賞を楽しめると思います。
かかる時間は?
こちらも演目により様々です。通しで1時間程度のところや、大きな祭礼では多数の演目を夜通し行うこともあります。事前に演目内容を確認し、自分のスケジュールも考えて鑑賞しましょう。
ここからは有名な神楽の演目についてご紹介していきます。
島根県・石見神楽
石見神楽は謡曲を神能化した出雲の「佐陀神能(さだしんのう)」が石見地方に伝わり、民衆の娯楽として演劇化されてきました。秋祭りの夜になると様々な神社から神楽囃子が聞こえてきて、祭は夜明けまで行われます。
演目は30種類以上になり、文化芸能としても広まっていて、現在では新しく創作された舞台演出で目を引くことのできる神楽になっています。
鈴神楽
演目の中で一番最初に舞う舞が「鈴神楽(すずかぐら)」です。こちらは1人で舞う舞で、手に鈴と扇を持って舞います。
「ちはやふる 玉の御すだれ巻き上げて 神楽の声をきくぞうれしき」
神前のすだれを巻き上げて、神楽をきくのは嬉しいという神様の立場で詠まれた歌になっています。
歌
奏楽は、大太鼓・締太鼓・手打鉦・横笛の4奏になっています。楽譜はなく、大太鼓の奏者がリードしながら奏されます。また、奏者は演奏しながら神楽歌を歌い、掛け声なども合わせて雰囲気を盛り上げる役目にもなっています。
前半はゆったりとしたテンポで始まり、後半にかけて一気にテンポを上げてクライマックスを盛り上げていきます。
演目リスト
鈴神楽(すずかぐら)
- 一番最初の演目です。1人で舞う舞で手に鈴を持って舞うため鈴神楽と呼ばれています。
塩祓(しおはらい)
- 1人または2人で舞います。四方祓いともいい、烏帽子(えぼし)に狩衣(かりぎぬ)姿で東西南北の四方を舞清め、神様を待つ準備の神楽です。
真榊(まさかき)
- 1人舞。こちらも鈴と榊を持ち四方を舞い清める神楽です。
帯舞(おびまい)
- 2人の舞手が帯を持ち、舞います。神の心を和らげる意味の舞で、衣・食・住の神に感謝の意を表す舞のうち、衣の神に感謝する舞になります。
神迎(かんむかえ)
- 4人で舞います。七五三縄(しめなわ)の中へまだ入っていない神様をお迎えするための神楽です。
八幡(はちまん)
- 武勇の神で、八幡宮の祭神である「八幡麻呂」を讃えるための神楽です。
神祗太鼓(じんぎたいこ)
- 「胴の口」ともいい、舞はなく囃子(太鼓、手拍子、笛)だけで演じる神楽です。
かっ鼓(かっこ)
- 「切目」と一連の舞。切目の王子に仕える神禰宜(かんねぎ)が羯鼓(かっこ)と呼ばれる太鼓を神様の気に入ってもらえる場所に据えようと四苦八苦する様子を滑稽な仕草で演じる神楽です。
切目
- 切目の王子が羯鼓を叩きながら舞う神楽。王子と介添えの2人の問答から始まります。
道がえし(ちがえし)
- 鬼反し(きがえし)とも言われます。鹿島神宮の祭神である武甕槌命(たけみかづちのみこと)が大悪鬼を退治する神楽です。
四神(よじん)
- 「笠(かさ)」とも呼ばれる4人舞。始めの手・中の手・三の手と歌舞、囃子が変化する複雑な舞です。
四剣(しけん)
- 4人で襷(たすき)をかけ、剣と鈴を持って舞います。神々を鎮め、舞殿を清める舞。
鹿島(かしま)
- 大国主命(おおくにぬしのみこと)の国譲りを題材にした神楽。
天蓋(てんがい)
- 天蓋の下に小天蓋を吊り下げ自由自在に躍らせる、曲芸的な神楽。
塵輪(じんりん)
- 塵輪とは翼を持った鬼のこと。石見神楽の鬼舞の代表的な演目です。
八十神(やそがみ)
- 大国主命が継兄弟の八十神と八上姫(やかみひめ)をめぐって争う様子を描いた神楽。
天神(てんじん)
- 学問の神である北野天満宮、太宰府天満宮に祀られている菅原道真公(天神様)の物語。藤原時平との戦いを創作されています。
黒塚(くろづか)
- 熊野、那智山の東光坊(とうこうぼう)の高僧、「阿闍梨祐慶大法印(あじゃりゆうけいだいほういん)が那須野が原で九尾の悪狐を退治する物語です。
鍾馗(しょうき)
- 鍾馗による病魔を司る疫神(鬼)を退治する物語です。石見神楽の花形とも言われる舞で厳つい面に豪華な衣装が定番になっています。
日本武尊(やまとたけるのみこと)
- 古事記にある日本武尊の物語。大野に入った日本武尊に八方より火を放ち、焼き殺そうとする兄弟との戦いの内容になっています。
岩戸(いわと)
- 天照大御神(あまてらすおおみかみ)の岩戸隠れの物語。天鈿女命(あめのうずめのみこと)が岩戸に隠れた天照大御神を華麗な舞で誘い出し、世の中に光を取り戻す内容です。
恵比須(えびす)
- 七福神でも有名な、商業、漁業の神様である恵比須様の鯛釣りの様子を舞ったもの。
大蛇(おろち)
- 石見神楽の代名詞とも言われる一番スケールの大きい神楽です。素戔嗚尊(すさのおのみこと)による大蛇退治の様子を舞った神楽です。
五穀種元(ごこくたねもと)
- 日本書紀に書かれている保食神(うけもちのかみ)による、五穀豊穣を祈念する舞。
頼政(よりまさ)
- 源頼政(みなもとのよりまさ)による鵺(ぬえ)退治の物語。
八衢(やちまた)
- 鹿島に続く物語で、猿田彦神が天孫を先導するために出迎えた物語。猿田彦はこれにより道標の神としても奉られている。
熊襲(くまそ)
- 日本武尊と熊襲建(くまそたける)の物語。日本武尊はこれにより熊襲建から「たける」の名をもらい、日本武尊と名乗るようになります。
五神(ごじん)
国常立王の5人の王子の物語。農民の知識、哲学、倫理観、天文、暦数の説明、陰陽五行などが口上にある石見神楽最大の長編。
創作演目リスト
大江山(おおえやま)
- 大江山にいた酒呑童子(しゅてんどうじ)と呼ばれる鬼の退治の物語。
弁慶(べんけい)
- 弁慶と牛若丸(うしわかまる)の物語。弁慶が源義経の家来になるまでが描かれています。
鏡山(かがみやま)
- 享保9年(1724年)の春にあった「鏡山事件」という仇討ちの物語。歌舞伎の演目にもなっており、伝承されている物語を再構成し、創作されたものになっています。
三上山(みかみやま)
- 三上山にいた大百足(おおむかで)を退治する物語。俵藤太(藤原秀郷)が天慶の乱に赴く道中の話になっています。
有明(ありあけ)
- 佐賀の鍋島藩での「化け猫騒動」を神楽にしたもの。
加藤清正(かとうきよまさ)
- 戦国一の武将と言われる加藤清正公が朝鮮出兵の際に、味方の士気を上げるために虎退治したことが舞われています。清正は法華経の信者で、日蓮宗の寺院に祭られています。
広島県・広島神楽
ストーリー
広島神楽は、石見神楽を基に出雲神楽や九州の岩戸神楽など様々な地方の神楽が融合し、独特に進化した神楽です。
その中でも大きく5つに分かれており、
- 芸北神楽
- 安芸一二神祗
- 芸予諸島の神楽
- 比婆荒神神楽
- 備後神楽
と呼ばれています。特に芸北神楽は、石見神楽を基に、江戸時代に広島県山県郡芸北地方に伝わり、八調子の早いテンポで進む勇壮な舞として有名です。
衣装
広島神楽は、演者の衣装が素晴らしく、舞の他にも見応えのある演出になっています。その物語に合わせて、衣装や面で感情を表し、観る人に出演者の気持ちが伝わりやすくなっています。また演目ごとに違う採り物(道具)にも注目して鑑賞してみましょう。
演目リスト
儀式舞(ぎしきまい)
- 神楽の始まりに、神様に感謝の気持ちを伝え、神様のお迎えをする舞を舞います。「神迎え(かみむかえ)」・「神降し(かみおろし)」・「塩祓い(しおはらい)」とも呼ばれ、東西南北の四方を清めるための舞になっています。
鍾馗(しょうき)
- 鍾馗が疫神を退治する話です。見えない疫神に対して矛で輪を作り、「矛の輪」を通して疫神の姿をとらえ、退治します。
岩戸
- 天照大御神の「岩戸隠れ」のお話です。最も神聖視されている演目で、神楽の題材としては珍しいほのぼのとしたお話になっています。
八幡
- 宇佐八幡宮に祀られている八幡の神「誉田別命(ほんだわけのみこと)」が異国より飛来した「第六天の魔王」に立ち向かい、退治するお話です。八幡の神の御威徳を讃える神楽です。
恵比寿
- 七福神の「恵比寿様」を題材にしたお話です。祝賀式などでも舞われることがあり、えびす様のキャラクターを象徴した、愉快で滑稽な舞となっています。
天神
- 天神と崇められている菅原道真公と時の右大臣藤原時平の戦いの様子が描かれています。
塵輪
- 塵輪という大悪鬼との戦いの様子が描かれています。塵輪の面は神楽面の中では最大級で不気味です。
葛城山
- 源頼光の土蜘蛛退治のお話です。土蜘のおどろおどろしい面や衣装が人気になっています。
大江山
- 源頼光による酒呑童子という鬼の退治のお話です。登場人物が多く、クライマックスの入り乱れての戦いのシーンが見どころになっています。
神武
- 神武天皇が名を改め、日本国を建国した際の物語です。この演目は明治16年頃に創作され、広島県が生んだオリジナルの演目として知られています。
日本武尊
- 古事記にある、日本武尊(やまとたけるのみこと)の物語です。東夷征伐と熊襲征伐の2つのストーリーがあります。
戻り橋
- 先にあげた「大江山」の前篇にあたる部分です。大江山は長編の演目になっており、この「戻り橋」から「羅生門」・「大江山」へと続いていくストーリーになっていきます。
滝夜叉姫
- 平将門の娘である滝夜叉姫が藤原秀郷・平貞盛に復讐するために鬼女になるお話です。姫の面は鬼女の中でも最も恐ろしい形相で、姫の恨みが込められた悲しい物語となっています。
紅葉狩
- 鎮守府将軍・平維茂が戸隠山で紅葉狩りの酒宴を開いている女性にあい、酔い潰れてしまいます。これは鬼女の罠で襲われてしまうのですが、夢の中で八幡平菩薩より神剣を授かり、退治するというお話です。
黒塚
- 安達原の黒塚というところで祐慶法師が悪狐に襲われますが弓の名人、三浦介・上総介らが退治するお話です。
大蛇
- 素戔嗚尊(すさのおのみこと)による大蛇退治のお話です。広島神楽では8匹の大蛇が登場し、迫力満点の演目になっています。
大分県・庄内神楽
33の演目
庄内神楽は江戸時代末期から伝わる伝統芸能で、演目は33程で構成されています。
大きく分けて、深山流神楽と犬山流神楽に分かれており、現在10の神楽座が公演、奉納を行っています。
5月から10月の間、定期公演も行われていて、月に1度開催されています。
あらすじ
古事記・日本書紀に登場する神話が中心となっており、神様への感謝と威光を奉じた舞になっています。
五方礼始(ごほうれいし)
- 神楽を奉納するにあたり、五方(東・南・中央・西・北)を清める舞です。
天瓊矛(あまぬのほこ)
- 伊邪那岐尊(いざなぎのみこと)と伊邪那美命(いざなみのみこと)が天の浮橋に立ち、自凝島(おのころじま)を造ったお話です。
平国(へいごく)
- 伊邪那岐尊が御子の加具都智神(かくづちのかみ)をお斬りになった時に岩裂神(いわさくのかみ)・根裂神(ねさくのかみ)・岩筒男神(いわつつおのかみ)・経津主神(ふつぬしのかみ)がお生まれになったお話。各神の荒魂を鎮める舞です。
舞入
- 伊邪那岐尊と伊邪那美命が、天照大御神・月読尊・素戔嗚尊をお産みになり、自凝島にお隠れになるお話です。
誓約(うけい)
- 天照大御神が十握剣(とつかのつるぎ)から三柱の女神、素戔嗚尊が五百箇御統(いほつみすまる)の瓊から五柱の男神がお産まれになったお話です。
戸開(とびらき)
- 古事記の「天の岩戸」を題材にした舞です。
柴引(しばひき)
- 天の岩戸開きを祈って、奉納するため、天香山(あまのかぐやま)の真榊を根こそぎにするというお話です。
庭火(にわび)
- 天の岩戸前で天鈿女命(あめのうずめのみこと)が踊る際の庭火(かがり火)をたく形の舞です。
神逐(かみやらい)
- 岩戸隠れの際に、悪行の素戔嗚尊を高天原から根の国に追放するお話です。
岩戸舞(いわとまい)
- 岩戸隠れの後に八百万の神が天の岩窟(いわや)の前で喜んで舞を舞ったお話です。
神開(かんびらき)
- 八百万の神が岩戸開きを祝って天の安河原に集まり、和魂を起こし給う舞です。
本剣(ほんつるぎ)
- 岩戸開きをお祝いする剣の舞です。
鹿児弓(かごいれ)
- こちらも岩戸開きを祝う舞です。八百万の神々が「天之鹿児弓(あまのかごゆみ)」と「天羽羽矢(あまのははや)」を持って舞うお話です。
柴入(しばいれ)
- こちらも八百万の神々が天香具山の榊を手にして喜びを表す舞です。
二草(ふたくさ)
- 天照大御神が八百万の神に葦原中津国(あしはらなかつくに)の邪神を平定するお話です。
五穀蒔(ごこくまき)
- 八百万の神が、天狭田・長田に植えた稲の豊穣を祝う舞です。
大蛇退治(おろちたいじ)
- 素戔嗚尊の大蛇退治のお話です。庄内神楽で最も勇壮な舞となっています。
返杯(へんはい)
- 素戔嗚尊が根の国から帰ってくる状の舞です。
心化(しんか)
- 誓約でお生まれになった男神五柱・女神三柱の男女の神が人間を善に導くというお話です。
返し矢(かえしや)
- 天照大御神が国譲りの使いとした天若日子(あまのわかひこ)と別の使いの雉(きじ)の物語です。
国司(くにつかさ)
- 日本の神話の中の出雲地方のために降到りする神話を題材にしています。
魔払(まはらい)
- 天照大御神が八百万の神に中津国の邪神を平定させるお話です。
天孫降臨(てんそんこうりん)
- 天照大御神から三種の神器を授かった瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)が猿田彦尊(さるたひこのみこと)の案内で中津国に降りるお話です。
太平楽(たいへいらく)
- 天孫降臨後の天下太平を喜び舞うお話です。
貴見城(きけんじょう)
- 古事記の海神宮(わだつのみや)を題材とし、瓊瓊杵尊の子である火闌降命(ほのすそりのみこと)と彦火火出見命(ひのほほでみのみこと)の兄弟のお話です。
高座返し(たかざかえし)
- 神楽の無事奉納を祝う舞。
日割(ひわり)
- 庄内神楽独特の舞です。古代中国の易経の中から取題したもの。四季を5等分に日割する暦作りの舞。
綱伐(つなきり)
- 大蛇退治の原型の舞です。五穀豊穣・無病息災・家内安全などの祈願で奉納されます。
布晒(ぬのさらし)
- 織女の天八千千姫命(あまのやちぢひめのみこと)と鳥船命(とりふねのみこと)による喜劇のような舞です。
五穀舞(ごこくまい)
- 保食神(うけもちのかみ)の死体から、五穀や牛馬が生まれ、天の田畑に種を蒔いたお話です。
大神(だいじん)
- 天孫降臨が無事終わったことを祝う舞です。
綱之武(つなのたけ)
- 素戔嗚尊が天照大御神の御田を荒らし、数々の暴挙をつくしたため、八百万の神と闘うことになったお話です。
見どころ
テンポが早く、勇壮、かつユーモラスな動きを合わせた見応えのある神楽です。特に「大蛇退治」という演目は、迫力があり、ストーリーも分かりやすく大人から子供まで楽しめる演目になっています。
【まとめ】神楽の演目について
- 神楽とは神様に捧げる舞のため、その演目は古事記・日本書紀にある、神々の神話が多い。
- 演目あたりの時間は様々で、行事自体の時間は1時間から、長いものは夜通し神楽を舞うお祭りもある。
神楽は神道での神事で奉納される神事ですが、今では文化芸能としての面も大きく、それぞれ鑑賞舞台としても見応えのあるものが多くなっています。
歌舞伎や能、日本舞踊など、日本には伝統芸能と呼ばれるものはたくさんありますが、その中でも神楽は日本の成り立ちである古事記や日本書紀の世界を堪能できる素晴らしい芸能であると思います。
皆さんもぜひ、神楽の世界に没頭してみて下さい。
神楽の創作舞はこちら