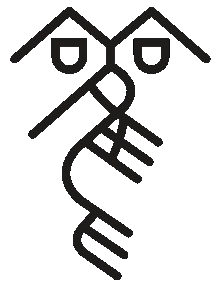神楽の音楽「神楽歌」は90種を超える?【オススメ8選】

神社での神事や芸能として地域のお祭りなどで見ることのできる神楽舞ですが、そこには必ず楽曲があります。
日本古来の雅楽と呼ばれる楽器を使った、荘厳で優美な演奏を聞いたことがあるでしょう。
今回は神楽の楽曲についてご紹介いたします。
舞の美しさに気をとられるところも多いと思いますが、その楽曲もまた多種にわたり、古来より伝承された素晴らしいものになっています。きっとその奥深さに興味が湧いてくると思いますよ。
巫女神楽の創作舞はこちら
神楽の音楽について
神楽の始まり
神楽は、神道の神事で神様に奉納するための歌舞として、日本最古の芸能とされています。
神楽の語源は「神座(かむくら・かみくら)」と言われており、「神様の宿るところ」という意味で、神座に神様を降ろし、巫女により人々の穢れを祓ったり、神懸かりを行い人々との交流をする場所となり、ここで行う歌舞が神楽と呼ばれるようになりました。
起源は古事記・日本書紀にある「岩戸隠れ」という神話からとなります。
この物語では太陽神「天照大御神(あまてらすおおみかみ)」が岩戸の中に閉じこもってしまった際、技芸の女神である「天鈿女命(あめのうずめのみこと)」が岩戸の前で舞を披露し、天照大御神を岩戸の中から誘い出したのです。
また、天鈿女命の子孫とされる「猿女君(さるめのきみ)」が朝廷の祭祀の際に舞い、招魂・鎮魂のための儀式として定着していったのです。
神楽歌は約90種
神楽は平安時代中期に様式が完成し、使われる神楽歌は約90種にのぼります。
主に知られるのは37曲で
庭燎(にはび)
- 宮中参内の諸臣のために焚いたかがり火のこと。
阿知女(あちめ)
- 神や精霊を招くための呪文。阿知女作法(あちめのわざ)とも言われる。阿知女は天照大御神のこと。
採物歌(とりものうた)
- 榊(さかき)、御幣(みてぐら)、杖(つえ)、篠(ささ)、弓(ゆみ)、剣(たち)、鉾(ほこ)、杓(ひさご)、葛(かつら)、韓神(からかみ)などの採り物(舞の際に手に持って使われる道具)を使用した舞に使われる10曲。
大前張(おおさいばり)
- 「前張」のひとつで歌詞は短歌の形式に近い。「宮人(みやびと)」、「木綿志手(ゆふしで)」、「難波潟(なにはがた)」、「前張(さいはり)」、「階香取(しなかとり)」と呼ばれる5曲。
小前張(こさいばり)
- 「前張」のひとつ。民謡色の濃い歌。薦枕(こもまくら)、閑野(しづや)、等前(いそらがさき)、篠波(ささなみ)、植舂(うえつき)、総角(あげまき)、大宮(おおみや)、湊田(みなとだ)、蟋蟀(きりぎりす)、千歳(せんざい)の10曲
早歌(はやうた)
- 小前張の部の最後に歌われる歌。早いテンポで、ユーモラスな問答風の歌詞になっている。
星三種(ほしさんしゅ)
- 吉吉利利(ききりり)本来は「きりきり」だったようです。神楽歌の中では唯一の漢文的歌詞の曲。「明星(あけぼし)とも言われます。
- 得銭子(とくせんこ)本来は特選子で、御厨子所の女官「特選」を親しみを込めて呼んだ言葉。
- 木綿作(ゆふつくる)木綿をつくる人のこと。
雑歌(ざっか)
- 昼目(ひるめ)昼目の神ということで大日女(おおひるめ)の別名のある天照大御神のことと言われています。この曲は秘曲と言われており、大嘗祭で行われているとされています。
- 立弓(ゆだち)弓の射手が弓を構えて立つことの意味。
- 朝倉(あさくら)天智天皇の歌として新古今和歌集に収録されている歌が元。「朝倉(福岡県朝倉市)の木の丸殿にいったおり、宿直の名乗りをしていったのは誰の子であろうか」と歌われています。儀式の後半、終わりに近づいた頃に歌われる曲です。
- 其駒(そのこま)神の乗り物の駒を歌って惜別の情を表しています。宮中御神楽で最終部に歌う曲。
竈殿歌(かまどのうた)
- 竈殿遊歌(かまどのあそびうた)とも言われ、歌の詞は「素晴らしい竈の前で神遊びをすると、天の河原に久しく声が届く」といった内容になっています。
酒殿歌(さかどのうた)
- 酒殿は酒をつくるための建物です。詞の内容は「酒殿は大変広い。酒を入れるかめ越しに手をつかまないでください。そうは言ってないのに。今日は酒殿を掃除する必要はありません。舎人女が掃いてくれたので。」となっています。恋の歌にも聞こえますが、諸説あり実際の意味は確定されていません。
となっています。場所や人、物など多種にわたる題材で構成されており、その意味はいまだに解明されていないものも多いのです。
神楽を伝える者たち
神楽は現在でも日本全国で伝承され、受け継がれています。神楽は大きく分けて、宮中で行われる「御神楽(みかぐら)」と民間で行われる「里神楽(さとかぐら)」に分けられ、私たちが普段目にする物の多くは里神楽に分類されます。
里神楽は、巫女による「巫女神楽」、採り物神楽とも言われる「出雲流神楽」、湯立神楽とも言われる「伊勢流神楽」、山伏神楽、太神楽とも言われる「獅子神楽」に分かれています。
巫女、出雲、伊勢、山伏など、伝承される種類や内容は様々ですが、全て神座を設けて、神様の招聘をもって執り行われています。
これは文化の伝承でもあり、神様にむけた畏敬や感謝の気持ちを伝えるための方法で、私たちの生活に寄り添い、日常に密接に関わっているものと言えるでしょう。
巫女神楽の創作舞はこちら
おすすめ!神楽の音楽を聞きたいならコレ
ここでは神楽の音楽を楽しめるCDと動画をご紹介します。
どれも聴きやすいものになっていますが、しっかり神楽の世界を楽しめると思います。是非聴いてみてください。
御神楽
伏見稲荷大社での御神楽の動画です。笛、和琴、篳篥などの雅楽楽器の美しい音色に合わせて「人長舞」が舞われます。
笛演奏〜「通り神楽」
雅楽では「吹物(ふきもの)」と呼ばれる管楽器が主旋律を奏でるのが一般的です。笙(しょう)、篳篥(ひちりき)、龍笛(りゅうてき)など様々な種類の管楽器で幅広く、深みのある音の重なりを感じることができます。
石見神社×万葉音楽祭
島根県石見地方では「石見神楽」と呼ばれる特色のある舞を見ることができます。日本神話を題材とした演劇の要素を持った神楽となっており、最近では有名アーティストとのコラボレーションにより、さらに進化した神楽を見ることができます。
万葉音楽祭2017DragonAshのATSUSHIコラボ「大蛇」
【まとめ】神楽の音楽について
神楽の始まり
- 神楽は神様に奉納するための歌舞で日本最古の芸能
- 起源は日本最古の書物である古事記・日本書紀にある「岩戸隠れ」の神話
- 朝廷の祭祀の際に舞われ、定着していった。
神楽歌は約90種
- 神楽で使われる神楽歌の種類は約90種におよぶ。
- 主に使用されるのは37種。
神楽を伝えるものたち
- 神楽は宮中でおこなわれる「御神楽」と民間でおこなわれる「里神楽」に分けられる。
- 里神楽は「巫女神楽」、「出雲流神楽」、「伊勢流神楽」、「獅子神楽」に分かれており、それぞれ巫女・山伏や、その地方での伝承により形を変えて受け継がれている。
実際神楽を見るとその舞の素晴らしさに目を奪われてしまいますが、その舞を支える曲「神楽歌」もとても心に響く曲ではないでしょうか。神楽において舞と歌は一対でどちらもなくてはならないもので、この二つがきれいに重なることで成り立っているのです。雅楽楽器の響きと、時代を重ねて深みを兼ねたその旋律を楽しんでみてください。