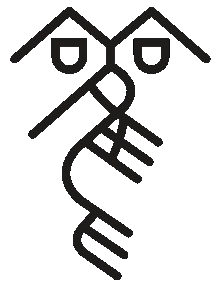巫女の衣装とは?白衣、緋袴、千早…など巫女装束を徹底解説

参拝や観光で神社を訪れた際に、目を引く存在と言えば「巫女」でしょう。特に印象的なのはその衣装で、あの白い上衣に赤い袴は、厳かな神社の雰囲気の中で神聖さを感じることができると思います。
では実際の巫女の衣装とはどのようなものなのでしょう。あの白い服や、赤い袴の意味、祭祀の際の衣装など詳しく知っている方も少ないと思います。ここでは巫女の衣装について詳しく解説していきたいと思います。
同じに見える巫女の衣装も神社によって違いもあり、そんな観点から見比べてみるのも興味深いところではないでしょうか。
元巫女による創作舞はこちら
巫女の衣装とは?
現在の白い小袖(白衣)に赤い袴(緋袴)の巫女の衣装は明治時代に定着されたものです。神道が国教として制度が見直された際に神社巫女という分類がなされ、現在の巫女が誕生しました。平安時代頃には特に決まりはありませんでしたが、室町時代の初期から赤い袴が定着していったとされ、現在の装束に落ち着いたのです。
この巫女や神職については使用する色は重要で、
- 「黄櫨染」は天皇の色
- 「黄丹」は皇太子の色
となり、「禁色」として使用することはできません。
また、葬儀に用いられる
- 「鈍色」
- 「鼠色」
も「忌色」として通常の使用は禁じられています。
巫女装束の3原則
巫女装束には3原則と呼ばれるものがあり、丁重に扱うものとされています。
- 「投げるな」(脱ぎ捨てない)
- 「置くな」(着脱後はすぐに畳む)
- 「跨ぐな」(跨ぐ行為は神への非礼にあたる)
となり、巫女装束は「お札(護符)と同じ扱いをする」こととなっています。
巫女装束の色と年齢の関係
元々の巫女装束は年齢によって色が変化していたとされています。そして未婚の女性が着用していた色が赤色だったことから、緋色(赤色)の袴が一般的に用いられているようです。
神社によっては年齢によって色を変えるところや、金毘羅宮のように濃色(こきいろ)と呼ばれる濃い紫色の袴を用いているところもあります。
巫女装束については前述した白衣・緋袴の他にも使用される衣装があります。
ここからは巫女装束についてひとつづつご紹介していきましょう。
巫女衣装の詳細
白衣(はくえ・びゃくえ・しらぎぬ)
上半身にまとう白い小袖ですが、袖丈は留袖の長さになっています。小袖は元々下着でしたが、平安時代末期から鎌倉時代にかけて表着化していきました。
首元には赤い色の掛襟(かけえり)・伊達襟(だてえり)が使用されています。
緋袴(ひばかま)
下半身に履く、緋色の袴です。元々は平安時代の女官や貴族の女人が着用していた襠(まち)ありの捻襠袴(ねじまちばかま)が原型となっています。
捻襠袴は踝まで覆う長袴ですが、これは室内用になっており、巫女が用いるのは外出用に使われる壺装束用の切袴(きりばかま)となっています。
この投稿をInstagramで見る
千早(ちはや)
巫女が神事の奉仕や、巫女舞・神楽舞を舞う際に白衣の上に着る上衣です。
本来は白無地の絹一幅の中央部に縦の切り込みを入れただけの貫頭衣(かんとうい)のスタイルでしたが、後に絹二幅の構成となり、脇を縫わずに前を胸紐(むなひも)で合わせるスタイルに変わり、さらに袖が付けられて肩袖の根元だけが縫われた現在のスタイルになりました。袖や背、胸紐には朱色の装飾が施されている場合が多くなっています。
この投稿をInstagramで見る
水干(すいかん)
男子の平安装束のひとつです。狩衣に似て、丸襟の背縫いがない一つ身仕立てとなっています。
女子用としては白拍子(平安時代から鎌倉時代にかけて起こった歌舞。またはそれを演ずる芸人)が使用していたことが有名です。
1987年には公式の服制から外されましたが、現在でも神事の内容によって用いられる場合があります。
この投稿をInstagramで見る
裳(も)
後腰につける装飾で、腰から後へヘトレーン状に棚引かせる布。
女房装束の晴装束として用いられます。巫女舞の「浦安の舞」など神楽や神事で使われることがあります。
この投稿をInstagramで見る
羽織(はおり)
寒冷地では防寒として巫女用の羽織りを用いることもあります。この場合はウール製の裏付仕立てのものが一般的になります。
水引・丈長(みずひき・たけなが)
巫女は長い黒髪も装束のひとつとみなされており、その維持が求められる場合が多いようです。
その長い髪を後の生え際から下で束ねてひとまとめにし、檀紙(だんし)などで作られた丈長でまとめたり、和紙でまとめた上から水引で縛って髪留めとします。
この投稿をInstagramで見る
上指糸(うわざしいと)
袴につくねじられた2本の紐で、巫女独特の着付けとして、見えるように帯を結ぶことが多いようです。
履物(はきもの)
履物は白足袋を着用した上に草履か、白木の下駄が用いられます。下駄は黒塗りの場合もあり、鼻緒は赤か白が一般的です。
頭飾り(あたまかざり)
巫女舞などの儀式の際には、花簪(はなかんざし)や折枝、天冠などで装飾を行います。女性神職は額当(ぬかあて)を使用したり、神社によっては烏帽子を着用する場合もあります。
この投稿をInstagramで見る
採り物(とりもの)
祭祀や巫女舞を行う際に手に持つ小道具です。
- 榊(さかき)
- 御幣(みてぐら)
- 杖(つえ)
- 篠(ささ)
- 弓(ゆみ)
- 剣(つるぎ)
- 鉾(ほこ)
- 杓(しゃく)
- 葛(かずら)
- 鈴(すず)
- 扇(おうぎ)
- 盆(ぼん)
などが使用されます。
この投稿をInstagramで見る
酒器(しゅき)・他
神前結婚式などに用いられる
- 御神酒(おみき)や
- 屠蘇(とそ)
をいれる酒器で、注ぐ方に
- 銚子(ちょうし)や
- 瓶子(へいし)
受ける方には
- 杯(さかずき)や
- 升(ます)
などが使われます。
主な装束だけでもこれだけあり、神社によってはまた違った衣装を使用している場合もあります。
ここからは実際に購入したい方に、どこで購入できるのかもご紹介します。
元巫女による創作舞はこちら
巫女の衣装はどこで購入できる?
一番容易な方法としては通販サイトでしょうか。ここでご紹介した以外にもたくさんありますので気になった方は調べてみてください。
安価なものから本格的なものまで数多くの品揃えとなっています。
1998年から和装のネット販売をおこなっている老舗です。巫女衣装の他にも法被などオリジナル商品も取り扱っています。
安価で購入できることが魅力です。気軽に巫女装束を楽しめるでしょう。
この他にも実際に見て買うことのできるお店も全国にたくさん存在しています。本格的に巫女の衣装に興味のある方は調べてみてください。
【まとめ】巫女の衣装とは?
巫女の衣装とは?
- 白衣に緋袴が一般的。
- 巫女舞の際は千早という羽織りと頭飾りで装飾を行うことが多い
- 禁色や忌色といった使ってはいけない色も存在する。
巫女装束の色と年齢の関係
- 巫女の装束の色は年齢により変化していた。
- 未婚の女性が使用していた朱色から現在の緋袴に定着した
- 現在でも年齢などにより色を変える神社もある。
- 金刀比羅宮の濃色のように独自の色の袴を使用しているところもある。
このように今では一般的になっている巫女の衣装ですが、時代や土地柄によって様々な形式が出来上がっているのです。
特に巫女の舞う巫女舞では神社によって違いがあり、舞の型や演目の他にも巫女の衣装にも注目してみるのも楽しみのひとつとなるのではないでしょうか。皆さんも地元の神社での祭祀やお祭りの他にも観光で神社に訪れた際は、巫女の衣装にも注目してみてください。きっと新しい発見が見つかると思いますよ。