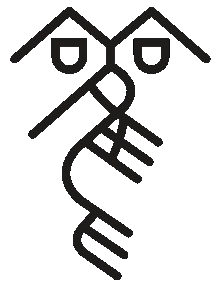沖縄のノロとは?ノロの起源、役割、家系やユタとの違い

沖縄には、ノロといわれるシャーマンがいます。沖縄には他にもユタと言われるシャーマンがおり、役割も少し違っています。
今回は、この「ノロ」について
- ノロとは何か
- ユタとの違い
- ノロの起源・役割
- ノロの家系
について詳しく見ていこうと思います。
この記事を読み終わったころには、ノロとはどういうものか、ノロとユタの違いなどについて分かるようになります。
沖縄の神様からいただいた舞はこちら。
沖縄のノロについて
ノロとは?
ノロ(祝女)は、琉球神道における女性の祭司です。
地域の祭祀を取りしきり、御嶽(うたき)と呼ばれる場所で、祭祀を司っています。琉球神道というのは、琉球王国を中心に信仰されてきた多神教宗教です。神話や自然崇拝の、アニミズム的かつ祖霊崇拝的な宗教です。
ノロは、このアミニズム的な考えによる琉球の神々と交信ができる存在です。祭祀の間はその身に神を憑依させ、神そのものになると考えられており、神人(かみんちゅ)と呼ばれることもあります。
ノロは15世紀の琉球王国で、王が祭政一致により支配を目的として巫女組織を制度化する中で位置づけられた神職です。そのため、公的な祭祀者とされています。
では次に、ノロとユタの違いをみていきます。
ノロとユタの違い
ノロが公的な神事や祭事を司るのに対して、ユタは市井に暮らし一般の方を相手に霊的助言を行うシャーマンです。
- ノロ = 公的なシャーマン
- ユタ = 市井のシャーマン
という位置づけです。
沖縄では、「困ったらユタに聞け」と言われるくらい、ユタは人々の生活の中に根付いています。
ノロは、公的な役割を担う、少し位の高いシャーマンと言えるでしょうか?
続いて、ノロの起源をみていきます。
ノロの起源は?
では、「ノロ」という呼び名はいつからできたのでしょうか?
先ほども少し述べましたが、15世紀に巫女制度が組織化されました。その時、神職の正式名称として「ノロ」という呼称が制定されました。
ノロというのは、神職の名前なのですね。
続いて、ノロの役割をみていきます。
ノロの役割
ノロは村において、憑依巫女やユタやニーガン(根神)という他のシャーマンを導く立場にあります。市井のシャーマンのトップといった感じでしょうか。
ノロは
- 豊穣を願う
- 災厄を払う
- 祖先を迎える
- 豊穣を祝う
といった時期ごとにある数多くの祭祀を行います。
そしてその祭祀で、神を憑依させる依代となることが存在意義です。そのため、これといった戒律や教典はありません。また、他の宗教のように大衆に伝える神の教えといったものもありません。
何かの教えを伝える役割というのではなく、神を憑依させ、祭祀の中で人々の幸せを願ったり、厄を祓ったりという役割なのですね。
ここまでで、ノロとは何か、ユタとの違い、ノロの起源・役割についてみてきました。
続いて、沖縄のノロの家系についてみていきます。
沖縄の神様からいただいた舞はこちら。
沖縄のノロの家系について
ノロは世襲制「ノロ殿地 (どうんち)」
ノロは世襲制となっており、「祝女殿地(のろどぅんち)」と呼ばれる家系から出ています。
先にも少し述べたように、琉球王国時代に王府より任命された家系になります。もともとは、各地域の有力な王族の肉親であったと考えられています。
始まりは琉球王国時代
前にも少し述べましたが、ノロの始まりは15世紀の琉球王国です。
琉球王国では尚真王(しょうしんおう)と言われるトップにより、祭政一致による支配を目的として、神女組織が制度化されました。
組織は次のように、上から位が高くなっています。
- 聞得大君(ちふぃじん)=王府の最高神女
- 大阿母志良礼(うふあむしられ)=3人いる
- 三十三君(さんじゅうさんくん)=上級神官、上級ノロ
- ノロ=各地のノロ
という組織になっています。
聞得大君を頂点に、ノロは琉球政府の神女組織に属し、村の祭事を司りました。聞得大君以下すべてのノロは、王府の任命制でした。
尚真王以降、神女組織は力を失っていきます。そして1897年の琉球王国の解体とともに、ノロは公的地位を失っていきます。
琉球王国の発展・衰退とともに、ノロの地位も変わっていったようですね。
交信対象は守護神やニライカナイの神々
ノロが信仰する琉球神道は、アニミズム的な多神教宗教です。このアミニズム的な考え方では、海の彼方のニライカナイと天空のオボツカグラという概念があります。
このニライカナイとオボツカグラに太陽神(ティダと呼ばれる)をはじめとする多数の神がいます。また生者の魂も、死後にニライカナイに渡って肉親の守護神になるとされています。この神々は、現世を訪れて豊穣をもたらし、人々を災難から守護すると考えられています。
ノロはこれら琉球の神々と交信することのできる存在です。また祭祀の間はその身に神を憑依し、神そのものになる存在とされていてノロは神人(かみんちゅ)とも呼ばれるのです。
ニライカナイやオボツカグラなど、その言葉の感じも、世界観も、沖縄ならではという感じですね。
それでは、これまでの内容についてまとめていきます。
【まとめ】沖縄のノロとその家系について
沖縄のノロとその家系について、これまでの内容を振り返っていきます。
・ノロは世襲制「ノロ殿地(どうんち)」
琉球王国時代に王府より任命された家系。もともとは、各地域の有力な王族の肉親
・始まりは琉球王国時代
ノロの始まりは15世紀の琉球王国。尚真王(しょうしんおう)と言われるトップにより、祭政一致による支配を目的として、神女組織が制度化された
・交信対象は守護神やニライカナイの神々
ニライカナイ・オボツカグラなどの他界の神が信仰対象。死後にニライカナイに渡って肉親の守護神になる生者の魂も信仰対象
沖縄のノロは、琉球王国の時代から王府に認められた格式高いシャーマンと言えます。日本のシャーマンであるノロに、このような歴史があるなんて、面白いですね。
沖縄の神様からいただいた舞はこちら。