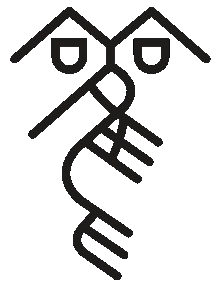皇室神道とは?歴史から読み解く皇室と神道の関係性

天皇陛下(明仁さま)が4月30日に退位し、皇太子徳仁親王さまが新天皇に即位されました。年号も平成から令和と新しい時代がスタートしましたね。そのことをキッカケに令和の由来になった和歌が納められている「万葉集」や明仁さまや美智子さまのご本が本屋でよく見かけるようになりました。それにより皇室の歴史など気になり様々な記事を読んでいる方も多いのではないでしょうか。
今回は皇室の中でも「皇室と神道の関係」という視点で深く掘り下げていこうと思います。
皇室も神道もとても長い歴史を持っていますので
- 皇室と神道について
- 皇室神道の歴史
に分けてわかりやすくご紹介していきます。
この記事を読むことで我々日本人が日常の中に自然と考えが受け継がれている「八百万の神様」である神道と皇室の関係性が分かり、どうして今もなお神道が受け継がれているのかが分かりますよ。
元巫女による古式巫女舞をベースにした舞はこちら
皇室と神道について
神道とは?
まずは神道の定義についてみてみましょう。
神道(しんとう、しんどう)は、日本の宗教。惟神道(かんながらのみち)ともいう。教典や具体的な教えはなく、開祖もいない。神話、八百万の神、自然や自然現象などにもとづくアニミズム的・祖霊崇拝的な民族宗教である。
自然と神とは一体として認識され、神と人間を結ぶ具体的作法が祭祀であり、その祭祀を行う場所が神社であり、聖域とされた。明治維新より第二次世界大戦終結まで政府によって事実上の国家宗教となった。この時期の神道を指して国家神道と呼ぶ。(引用:Wikipedia)
多種多様な数多くの神という意味をもつ「八百万の神様」と言う言葉はこの神道の考えです。水や火、木や花などの自然物から消しゴムや筆箱などの物、建物までも神様が宿っていると考えられています。また、幼少期の頃親や祖父母から「悪いことをしたらいかん。お天道様が見ているよ」と言われながら育った方もいらっしゃるのではないでしょうか。この考えもまた神道の考えです。
このように我々日本人の日常の中に自然と取り入れられているのです。
より神道とは何か知りたい・興味がある人は下記記事で詳しく紹介していますので、見てみてください。
「神道の歴史を深堀り!起源から現代神道に至るまでを簡単解説」
神道の種類
キリスト教にもカトリックやプロテスタントがあるように、神道にも種類があり大きく分けて3つあります。
- 皇室神道
- 教派神道
- 国家神道
詳しくみていきましょう。
- 皇室神道
天皇が古代から行ってきた宮中祭祀を中心とする神道が「皇室神道」です。
明治時代以降になると恒例祭祀・即位儀礼・喪葬儀礼などの法律に定めましたが、第二次世界大戦後になると四方拝や新嘗祭などの祭祀・儀礼は天皇の私事となりました。行う主な理由は、神に国家と国民の安寧を祈願することが中心です。
- 教派神道
教派神道とは、明治維新後に起きたの神仏分離の動きに伴い政府に認可された14の神道系教団(神道十三派)を指す言葉です(のちに1団体が離脱し13団体となりました)。
現在の神道十三派は次の流派になります。
- 神道大教
- 黒住教
- 神道修成派
- 出雲大社教
- 枎桑教
- 實行教
- 神道大成教
- 神習教
- 御嶽教
- 神理教
- 禊教(正式には「示」へんではなく「ネ」と書く)
- 金光教
- 天理教
- 国家神道
明治時代以降に国が神社神道と皇室神道を結びつけてつくり出した神道のことを言います。
神道を国家神道として定め、国民を統合するため国民に天皇制国家への忠誠を命じるとともに祖先崇拝を強調しました。しかし、1945年(昭和20年)にGHQによる神道指令「国家神道」の廃止が命じられたことにより、なくなりました。
皇室は神道なのか仏教なのか
素朴な疑問として、皇室は神道なのでしょうか?仏教なのでしょうか?皇室とそれぞれの関係をみていきましょう。
- 神道と皇室
まずは皇室神道の中心となる天皇と神道の関係を歴史をたどりながら見ていきましょう。
奈良時代に記された日本最古の歴史書である古事記や現存する最古の正史の日本書紀では、天上の世界である高天原(たかまがはら)を統治する天照大神が天皇家の始祖であるとしています。その天照大御神が地上を統治する役目を任せたのが、瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)です。この瓊瓊杵尊の曾孫が初代天皇とされている神武天皇だと言われています。
実際、この古事記と日本書紀は国の内外に天皇とは神聖なものであると知らしめる目的で行われていました。
- 仏教と皇室
続いて、仏教と皇室の関係を見ていきましょう。
仏教が伝来してきたのは6世紀中盤の飛鳥時代です。当初は仏教の受容をめぐり対立しましたが、仏教を信仰している蘇我馬子が権勢を握ることで仏教は徐々に社会に受け入れられてきました。用明天皇の皇子である聖徳太子も仏教を信仰し、天皇家にとっても信仰の対象として仏教が重要な存在になっていきます。奈良時代になると神道と仏教を一体化させる流れ(神仏習合(しんぶつしゅうごう))が作られより国民に受け入れられるようになりました。
葬儀も聖武天皇から孝明天皇まで仏式で行われていました。このことから皇室は神道・仏教どちらにも深い関わりがあることが分かります。しかし明治天皇の代で行われた神仏分離や神道国教化に伴い、仏教との直接的な関係は薄れ現在では完全に神道へ変わりました。
現在は神道である皇室ですが、神道と皇室の出会いや関係性をより深く掘り下げるために、次章では「皇室神道の歴史」についてご紹介したいと思います。
元巫女による古式巫女舞をベースにした舞はこちら
皇室神道の歴史
神道、皇室の歴史はとても長いため下記9つの項目に分けてご紹介していきます。
- 欽明天皇と日本書紀
- 聖武天皇と東大寺大仏建立
- 平安・鎌倉時代「即位灌頂」
- 「神仏習合」と「神仏分離」
- 明治時代、仏教が一掃される
- 明治天皇と伊勢神宮参拝
- 神道が宗教の枠から外される
- 天皇と天神地祇
- 現代の天皇と神道
ではそれぞれ見ていきましょう。
欽明天皇と日本書紀
第29代欽明(きんめい)天皇に関して記している第19巻には、仏教が朝鮮半島の百済(くだら)から日本へはじめて正式に伝来した経緯、いわゆる「仏教公伝」のエピソードが詳しく記されています。
百済から美しい仏像を受け取った欽明天皇は大変喜びましたが、そのまま仏教を受け入れることには躊躇する気持ちがありました。そこで家来に聞いてみると崇仏派と排仏派に意見がわかれたため、崇仏派である蘇我馬子の父蘇我稲目(そがのいなめ)に仏像を託します。この仏教の受容をめぐった対立は決着がつかず蘇我馬子まで引き継がれました。
結果、蘇我馬子が権勢を握り仏教は徐々に社会に受け入れられてきました。
聖武天皇と東大寺大仏建立
第45代聖武天皇は仏教の教えを取り入れた国造りを積極的に進めた人です。
当時の奈良時代は皇族、貴族の争いごとが絶えず、飢饉や伝染病も流行していました。その状況を見た聖武天皇は「どうしたら人々が幸せに暮らせるだろうか」と考えました。そこで奈良に巨大な大仏を建立し、様々な災いが鎮まることを祈ったのです。それが「東大寺」です。
その建立作業は745年から始められ9年かけてのべ200万人以上が大仏作りに関わったとされています。また聖武天皇はその他にも全国各地に国分寺(こくぶんじ)、国分尼寺(こくぶんにじ)も設置しました。
平安・鎌倉時代「即位灌頂」
Wikipediaの説明がわかりやすいので、そのまま引用します。
即位灌頂(そくいかんじょう)とは、11世紀ないし13世紀から江戸時代にかけて、天皇の即位式の中で行われた密教儀式で、その内容は秘儀とされていた。
一般的には即位式の前に摂関家、主に二条家の人物から天皇に対して印相と真言が伝授される「印明伝授」と呼ばれる伝授行為と、即位式の中で天皇が伝授された印明を結び、真言を唱える実修行為を併せて即位灌頂と呼んでいるが、印明伝授と即位灌頂の実修を明確に区別する研究者もある。ここでは印明伝授と即位灌頂を併せて説明する。(引用:wikipedia)
元々はインドで行われていた即位・立太子の儀礼であるこの即位灌頂は江戸時代孝明天皇まで行われていた仏教儀式です。印相とは手の指で様々な形を作り仏様の御利益や担当部門、意志などを象徴的に表します。お寺にある仏像の手の形を見たことがあると思います。それが印相です。(参考:wikipedia)
「神仏習合」と「神仏分離」
- 神仏習合
神道と日本の仏教を融合したものを言います。いつ頃からそのような形になったのかは明確にはなっていませんが、平安時代ごろから理論的に説かれるようになったと言われています。
このように2つの宗教が融合するケースは世界から見ても大変珍しく、西洋では異なる宗教同士で争うことが殆どです。
なぜそのようなことができたかというと、次の3つが考えられます。
- 神道は多神教に類する宗教のため他の宗教を受け入れる柔軟性があった
- 仏教の考え方が日本人の考え方・性格・生活に合っていた
- 仏教にある「五明」と呼ばれる5つの専門領域の一つである「医方明」は当時は最先端医療であったため非常に魅力的であった
結果それぞれの考えの良いところを融合させた神仏習合ができ「仏様が本来の姿で日本の神様は化身である」という考えが生まれました。
- 神仏分離
神仏分離とは、奈良時代から続いていた神仏習合の慣習を禁止して、神道と仏教を区別させたことをいいます。
江戸時代後期の復古神道に伴い盛んになった思想で、明治政府によって神仏分離令が発令されました。明治政府は、神仏分離を行うことで、神道の国教化を図りました。一部の国学者の主導のもと、外来の宗教である仏教は国教にはふさわしくないとしてそれまで特権を持っていた仏教関係者の財産や土地を剥奪していきました。
明治時代、仏教が一掃される
こちらもwikipediaを引用します。
廃仏毀釈(廢佛毀釋、排仏棄釈、はいぶつきしゃく)とは、仏教寺院・仏像・経巻(経文の巻物)を破毀(破棄)し、仏教を廃することを指す。「廃仏」は仏を廃(破壊)し、「毀釈」は、釈迦(釈尊)の教えを壊(毀)すという意味。
中国においては3世紀以来廃仏の動きが強く、唐の韓愈や宋以後の朱子学派の廃仏論が大きな影響力をもった。とりわけ中国仏教史においては三武一宗の法難が有名である。
日本においては江戸時代から儒学の興隆でしばしば起きるようになったが、とりわけ明治初期に神仏分離によって神道を押し進める風潮の中で、多年にわたり仏教に虐げられてきたと考えていた神職者や民衆が起こした一連の動きを指すことが多い。各地で仏像・経巻・仏具の焼却や除去が行なわれたが、この事件が仏教覚醒の好機ともなり、日本近代仏教は廃仏毀釈をてことして形成されていった。(引用:wikipedia)
日本全国で貴重な仏像、仏具、寺院が破壊され、僧侶は激しい弾圧を受け、還俗(げんぞく)を強制されたりするなど仏教徒に対しても厳しい態度を取りました。さらには五重塔は二十五円(一説には十円)で売りに出されたとも言われています。
(還俗とは:僧が僧籍を離れて、俗人にかえること。)
明治天皇と伊勢神宮参拝
実は江戸時代までの敵台の天皇で伊勢神宮を参った天皇はいませんでした。初めて参拝したのが明治天皇なのです。
明治以前は天皇自身が伊勢神宮を訪れることはタブーとされていました。そんな中なぜ明治天皇が参拝されたのか、それは明治時代の状況をみると明らかになります。この時代国民を統合するため天皇は天照大御神の子孫であるという神道の考えを用いて国民に天皇制国家への忠誠を命じるため「国家神道」にする働きがありました。そのため明治天皇は天照大神が祀られている伊勢神宮に参拝したとされています。
神道が宗教の枠から外される
大日本帝国憲法明治政府は神道を宗教の枠から外し、神道は仏教やキリスト教とは異なるという考えを示しました。この頃の大日本帝国憲法では信教の自由も認められていたため、あえて宗教の枠から外すことで国民道徳として国民全体に神道の儀礼への参加を他宗教であっても行えるようにという思惑があったのです。
天皇と天神地祇
天神地祇とは全ての神のことをいい、天神は高天原(たかまがはら)に生まれた神、あるいは葦原の中つ国に天降った神、地祇はこの国土の神のことをいいます。天照大御神ももちろん天神地祇に含まれており、その子孫である天皇も天神地祇に含まれています。
現代の天皇と神道
戦後の日本国憲法では天皇は、
- 日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって,この地位は,主権の存する日本国民の総意に基づく(憲法第1条)
- 天皇は,日本国憲法の定める国事行為のみを行い,国政に関する権能を有しない(憲法第4条第1項)
と規定されています。
気になるのが天皇は何をしていらっしゃるのかではないでしょうか。多忙を極める天皇ですが、
- 国事行為関係(内閣関係)などの書類に天皇が目を通し決裁する「執務」
- 内外の客を招いて行う昼食会や夕食会である「午餐」「昼餐」「晩餐」「夕餐」
- 海外の訪問
という国にとって大事な業務を行う他にも、
- 宮中三殿などで、国家や皇室の繁栄を願うなどの祭儀を行う「皇室祭祀(宮中祭祀)」
も行っています。
つまり、天皇は神道の最高の祭司として現在も祭祀により国家と国民の安寧を祈願し続けているのです。
【まとめ】皇室神道について
では、最後にまとめに入ります。
皇室と神道について
神道とは?
- 多種多様な数多くの神神道は日本の宗教神道。
- 神道の起源は自然的に生まれた自然信仰。その歴史は非常に古く、縄文時代を始まりに弥生時代から古墳時代にかけてその原型が形成された。
- 信仰の対象は「八百万の神」つまりは全てのものに神が宿っているという考え。
- 神道では「死は穢れ」と考えられているため、神社では葬儀を行うことができない。
神道の種類
- 皇室神道
- 教派神道
- 国家神道
皇室は神道なのか仏教なのか
葬儀も聖武天皇から孝明天皇まで仏式で行われていたことから、皇室は神道・仏教どちらにも深い関わりがあることが分かる。しかし明治天皇の代で行われた神仏分離や神道国教化に伴い、仏教との直接的な関係は薄れ現在では完全に神道へ変わった。
今回は「皇室と神道の関係」について詳しく掘り下げてきました。より詳しく知りたいというかたは下記本がKidleで無料で読むことができます。祭祀と天皇家の歴史がより詳しく知ることができますよ。